ヴィオリスト
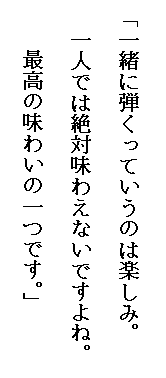 深井 碩章
深井 碩章
Hirohumi Fukai

2015年8月。世界的ヴィオリストである深井碩章さんに、桐朋学園大学時代の思い出と、ヨーロッパで導かれるようにして出会った楽器について語っていただきました。
――この度はお忙しい中、当団の演奏会に駆けつけていただいて、ありがとうございます。 深井先生とヴィオラとの出会いについて教えてください。
僕の入っていた学校は東京の桐朋の音楽大です。斎藤先生たちが作った学校です。 彼自身はチェリストで、ドイツで学んでこられたんです。斎藤先生が指揮をしながら、オーケストラが出来上がってきました。ただ当時は、芸大なんかはちゃんと試験があって、それに受からなければどんなに弾けても入れなかったんです。でも自分はそんなことどうでもいい、っていう先生で、弾ける人たちがすごくて、面白い。で、オーケストラが出来上がったはいいですけど、その当時はチェリストはいましたが、ヴィオラ奏者はいないなって。 結局、ヴァイオリンの学生たちが入れ替わり立ち代わりヴィオラを弾いて、オーケストラができるようになりました。最初に僕がヴィオラのトップをもらって弾いててね、僕の全然知らない曲でしたが、格好いいヴィオラソロの部分があったんです。僕が初めて弾いたら、みんながびっくりしちゃって。あ、ヴィオラってすごい、いい音だなって。
――今井信子先生の著書の中に、桐朋学園時代、まだよく音の出し方もわからないような古いヴィオラで深井先生がソロを弾かれて、その美しい音を聴いてみんながびっくりした、とありました。その時のお話ですか。
そう、宮本金八さんのね。まだ名前を憶えてる(笑)。学校にあった、当時の日本人が作ったっていっていう楽器(ヴィオラ)ね。そしたら斎藤先生が、「あなた、ヴィオラになったら?」って(笑)。
――桐朋学園大学時代に、ヴィオラとの出会いがあったんですね。
でもその時はまだ、「ヴィオラっていうのはこういうものか」、と。すごくいい音だなって。
学校時代にいろいろ室内楽を弾いたりすると、ヴィオラのセクションも大事なんですよね。「なんか物足りないな?」ってなると、(ヴィオラの担当の)楽器取り上げて、「こうやって弾くんじゃない?」とかやってましたね(笑)。
――先生が本格的にヴィオラに転向することになったのは、どういった経緯だったのでしょうか。
ジュリアードの試験があって受けたら、受かっちゃった。ヴァイオリンでジュリアードに入りました。ジュリアードっていうのは、皆「速度は私が一番早い」、「私が一番強い」って、そういう感じです。最初オーケストラの集まりがあった時、ブワーっと合わせると、「きたない音だな!」と思いました(笑)。
ニューヨークは騒がしいし、摩天楼ばかり。車はガーっと通っていく。これがニューヨークのオーケストラだ、と思いました。夏休みに、飛行機で大西洋を渡ってヨーロッパに行ったら、レンガ造りの屋根と緑がすごく綺麗だし、パリなんかは全然感じが違うんです。空が真四角じゃないし、しっとりとしてる。「あー、ヨーロッパ、いいなぁ」っていうのが最初の印象でした。
またヨーロッパに行ったとき、昔桐朋で習っていたフランス人の先生を訪ねたんです。僕は夏休みの講習会に行くつもりで楽器を持っていました。その先生が「ちょっと弾いてよ」、と言うので、ニューヨークで習ったのを弾きだしたら、しばらくして先生の顔が急に曇って、黙ってしまいました。しばらくしてから、「あなたはニューヨークに帰るつもり?あなたの演奏を見てると、…合ってない。」っていうんですよ。で、「いい友達がいるから、そこに行ったらどう? 手紙書いてあげるから、スイスに。」と。
そうして、スイスでシゲティ先生に習うことになりました。その頃から、急にいろいろと疑問を持ち出しちゃいました。静かだと、いろいろ考える余地がでてくる。 「自分はいったい、なんで音楽家なんだ」なんて考えてました。
思えば、母がピアニストだったので、子供皆に楽器やらせてました。でも、僕は全然ピアノがだめだった。母はそれを見て、「この子、だめだ」って(笑)。それでヴァイオリンを与えてくれた。7、8歳ごろでした。そうやってはじめたんです。
でも、このあと(自分は)どうしたらいいんだろう、と。母から手紙もくるし、もういいっていうのに(笑)。何だか反抗したくてしょうがない。少なくとも楽器を変えたら…「(母は)何も知らないんだし、うん、これはいいぞ!」って、思いつきました。それから考えがどんどん発展して、「ヴィオラで、もしかしたら自分の手で切り開いていけるかもしれない。」って思いました(笑)。
――導かれるように先生となる方に出会い、自分の手で世界を開きたいという強い思いもあったことで、転向が決まったんですね。
そう、楽器の話をしてもいいかな? さっきの練習で、この楽器、どんな響きをしていました?
実は前の楽器は素晴らしい楽器でした。これより小さいものでした。ヨーロッパでオーケストラに入団してから、仲間の人に「うちに一つだけ素晴らしい楽器があるんだ、それを絶対あなたに弾いてほしい、あれは特別だから」と言われたんです。
皆が言う楽器、そんなに良いのかな、と思っていたら、ある時僕のロッカーに、その楽器がぶら下がってました。それが真っ黒で。弦が一本だけ張ってあって。「汚い楽器だな」と思いました(笑)。「これが、皆が『良い』といってる楽器なの?」と。で、それまでの自分の楽器とこれと、弾き比べてみたら?ということになったんです。(楽器を見ないで)遠くで聴いてもらいながら、まず自分の楽器を弾きました。わざと、少し大きく(笑)。で、次にその汚い楽器を、『絶対、良いわけがわけないだろう』、と思って弾いたら、「あぁ、こっちが良い。」と言われました。
そうして、結局その楽器を弾くようになりました。楽器っていうのは、やっぱりそんなに違うんだな、と思いましたね。その楽器はね、中を見たらルジエリって書いてあって。ヴィオラ奏者であったヒンデミットの楽器って言われてるものです。
真っ黒になっていたのは、それを前に使っていた人が、「クリスマスに贈られたようなピカピカな楽器はいやだ」って使いっぱなしだったんです。松脂がもって真っ黒だった。だから僕が(磨かなきゃ)しょうがないから(笑)、磨きました。そしてその楽器で演奏会をしたら、すごい反響がありました。
今は引退して、「もう弾くことはないだろう」と思っていましたら、最後のお弟子さんがすごく優秀な人で、結局その楽器もっていかれちゃったんですよ(笑)。でも、若い人が弾いていた方がいいと思っています。
今の楽器(との出会い)は、スイスのベルンです。昔の生徒を訪ねた時、彼が「楽器に興味を持ち出して、オーケストラと両立しながら正式にマイスターの資格を取って、楽器を作ってます。」って、自分が作ったヴィオラをみせてくれた。弾いてみたら、「すごく弾きやすい」と思って。僕の奥さんも、「それ絶対買いなさい」って言うので。そういう風にして出会いました。時々ある室内楽の仲間にも、「あ、それいいんじゃない?」て言われてます。だから、いま、これがどんな響きがあるのかって、興味があるんです。
――楽器との人とのめぐりあわせですね。
そうですよね、音楽家っていうのはみんなそういうのありますね。
――合奏団の子供たちとの練習では、どのように思われましたか。
大阪音大で北浦先生に出会うことができたことは、僕にとってラッキーなことです。彼女が育てている生徒さんにちょっと会わせてもらったとき、「あ、すごいな」って思いました。北浦先生のクラスは飛び抜けているんですよ。その先生から今回初めてお誘いを受けたのですが、一緒に弾くっていうのは楽しみですね。一人で弾いてたら絶対味わえないですよね。オーケストラの、最高の味わいの一つっていうか、音楽をやる一番の楽しみです。子供達、みんな真剣な目ですよね。(練習の時、)テンポとか、「こうだよ」っていうと、すごいですよ、反応が。びっくりしちゃった。もちろん、北浦先生の力があるんでしょうけど、みんな、パッ、とのってくる。こういう、大事なスペースを作っていくのは大切なことでしょうね。本当に価値のあることです。
――子供たちは、本当に楽しんで演奏しています。いい音、いい音楽をたくさん聞かせてもらえていて、本当に幸せだと思います。
――今回は奥様もご一緒にお越し頂きました。よろしければ、奥様との出会いなど、お聞かせください。
出会いですか(笑)? 僕は当初、フランス語が全然できなかったから、フランス語が話せるチェリストの家に一緒に住むことになってて、フランス語を仕込んでもらってました。 夏休み、彼から「スイスのサンモリッツにいくから一緒に来ないか」って誘われました。 そしたらちょうど、彼女も休暇でサンモリッツにきていました。彼女はベルンのブティックで働いていてね、休暇をもらって避暑にきていました。初めてそこで会って、一緒に山に登ったりなんかして。そのあとベルンに行って、再会して(笑)。
彼女は自分も音楽をしたかったのですが、両親が反対してできなかったと。でも音楽会にはしょっちゅう行ってたから、すごく耳が肥えています。僕にとってはすごい批評家です。 怖いんですよ、彼女(笑)。
彼女の趣味は素晴らしい。音楽以上に、芸術に対していろんな事を知ってます。歴史から、何から。「あなた、そんなことも知らないの?」って言われちゃう。「日本にいるとき、そんなこと習ってないの?」って(笑)。いろんな事知っているっていうのはいいですよね。
――最後に、日本の音楽を志す若い人たちにメッセージをお願いします。
いろんな意味で、日本っていうのは恵まれていると思います。下地がものすごくあると。 日本人って、「音楽やっていました」という人が多くて、いろいろと詳しい。最近は、どんどん発展もしていって、もっとやりやすくなっていると思います。
ただ、日本人は積極性がたりないと言われることが意外とあります。僕は、そんなことないと思うんですけれど、まあ、日本人は最初からはっきりと(意見を)表現しないですよね。僕は生徒から「先生の言ってること、間違っています」なんて、最初からぱって言われるけど、(最初は)びっくりしちゃいました。日本では、そんなことありませんよね。今はどんどん変わってきているとは思うんですけど、もっと意思表示をはっきりした方が国際的にも間違われない。間違って取られやすいからね。音楽を通していってでもいいから、もっと近づいて行ったらどうでしょうか。
――ありがとうございました。移動と練習でお疲れのところ、たくさんお話を聞かせて頂いて、本当に嬉しく思います。演奏会当日も、先生の演奏を楽しみにしています。
≪深井碩章(ふかい ひろふみ)≫
鰐淵賢舟、村上信吾、鷲見三郎、J.イスナール、江藤俊哉の各氏に師事。’64年、日本音楽コンクール第2位(ヴァイオリン部門)。東邦学園大学卒業後、ジュリアード音楽院に入学し、I.ガラミアン教授に師事。’67年スイスで、巨匠ヨゼフ・シゲティに師事。同氏の教えを請う内に、ヴィオラに転向する決意を固め、スイス・バーゼル音楽院にヴィオラ奏者として入学。同音楽院にて、ヴィオラのソロ・ディプロマを受け、バルトークのヴィオラ協奏曲でデビューを飾る。同年、スイス・ベルン交響楽団にヴィオラの首席奏者として入団。 ’70年ハンブルク国立フィルハーモニーに入団し、’88年まで首席奏者となる。この間、クラウス・テンシュテット、シャルル・デュトワ、ホルスト・シュタイン、ヴォルフガング・サヴァリッシュ等の指揮者とヨーロッパ各地の主要オーケストラと共演し、ソリストとしても活躍する。また、アルド・チェッカート指揮、ロストロポーヴィチの共演で『ドン・キホーテ』をドイツ国内数カ所で演奏し、巨匠ロストロポーヴィチの厚い信頼を得る。’71年にはドイツ現代作曲家の巨匠ヘンツェが深井のために作曲したヴィオラ協奏曲の世界初演を行った。’74年からハンブルク国立音楽大学の正教授となり、後進の指導に当たる。また、’88年強い要請を受けて、北ドイツ放送交響楽団に入団し、首席ヴィオラ奏者を務めた。ソロ活動のみならず、室内楽の分野でも注目すべき活動を展開しており、ヨーロッパ屈指のヴィオラ奏者として、高い評価を得ている。